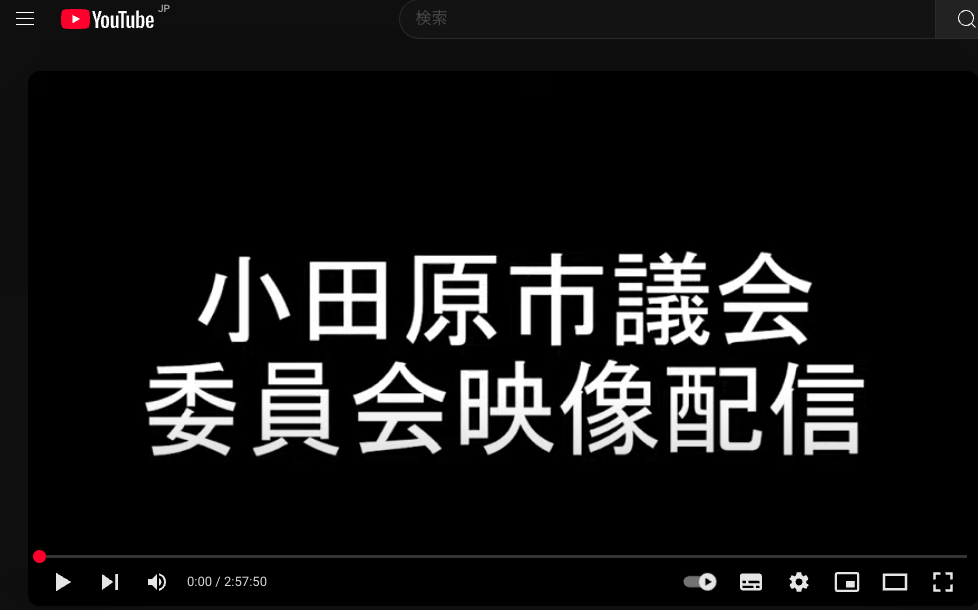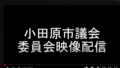- 総務常任委員会 議事録要約
- 議案審査(企画部関係)
- 議案第50号 令和7年度小田原市一般会計補正予算(所管事項)
- 議案第55号 小田原市職員の勤務時間休暇等に関する条例の一部を改正する条例
- 議案第56号 小田原市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
- 議題:議案第50号 令和7年度小田原一般会計補正予算(総務部関係)
- 議題:議案第50号 令和7年度小田原一般会計補正予算(市民部関係)
- 議題:議案第50号 令和7年度小田原一般会計補正予算(防災部関係)
- 議題:議案第63号 財産の取得について(ラップ式トイレ一式)
- 議題:議案第64号 財産の取得について(高規格救急自動車)
- 議題:議案第65号 財産の取得について(高度救命処置式等)
- 議題:議案第66号 財産の取得について(消防団活動他)
- 採決
- 議案審査(企画部関係)
総務常任委員会 議事録要約
日時: 令和7年6月12日
出席者: 委員、執行部(企画部、総務部、市民部、防災部、消防本部、上下水道局)幹部職員
(13:23) 議事調査担当課長:
- 議事の効率的運営のため、委員および執行部の質疑応答は簡潔明瞭にお願いしました。
- 本日の審査は提出事項の通り、お手元の審査順序に従って進めることに対し、異議なし。
議案審査(企画部関係)
議案第50号 令和7年度小田原市一般会計補正予算(所管事項)
(14:02) 企画部長:
- 補正予算書22〜23ページについて説明。
- 人事管理事業: 子供子育て支援法の改正に伴い、令和8年4月から新たに「子供子育て支援金」を職員給与から徴収する必要が生じるため、人事給与改修委託料を計上するものです。
(14:39) 質疑: なし。
議案第55号 小田原市職員の勤務時間休暇等に関する条例の一部を改正する条例
(14:59) 企画部長:
- 議案説明資料3〜4ページについて説明。
- 国家公務員における年齢に応じた柔軟な働き方実現措置の拡充に準じ、妊娠出産等の申し出をした職員に対し、仕事と育児の両立のための就業条件等について移行確認等の制度を設けるために改正するものです。
- 主な改正内容:
- 妊娠出産等を申し出た職員に対し、任命権者は育児休業承認の際の移行確認面談等の措置を講じなければならない(育児両立支援制度の周知、移行確認、支障となる事情の改善に係る移行確認)。
- 3歳未満の子を養育する職員に対しても同様の措置を講じる。
- 任命権者は移行確認した事項の取り扱いにあたり、当該移行に配慮しなければならない。
- その他、本改正に伴う字句等の修正。
- 施行日: 令和7年10月1日。
(18:31) 岩田委員:
- 本条例改正により、従前とどういった点で具体的な違いが現れるのか、また現れないのか。
- 人事配置上の違いが生じるかと思うが、どのような考えか質問しました。
(19:18) 職員副課長:
- 従前は育児休業制度の案内が主だったが、今回の改正により、育児休業だけでなく、部分休業制度や育児短時間勤務制度など、より幅広い両立支援制度を職員にきちんと説明し、利用意向を確認することが義務付けられる点が大きな違いです。
- また、3歳未満の子を養育する職員に対しても同様の措置を講じる点が新たに追加されます。
- 人員配置については、制度利用者が増えることは良いことであり、会計年度任用職員の確保や日常業務分担の中で体制を整えていきたい。
(21:05) 岩田委員:
- この制度の対象になる人数はどのくらいと想定しているか。
- 平均的に年間でどのくらいの人が利用し、それに対する代替人員はどれくらい増員する必要があると考えているか。増員は全体の中で調整するのか。
(21:50) 職員給与係長:
- 令和6年度の出生職員数は109名であり、出生時の移行確認対象は約100人前後になる見込み。
(22:46) 職員副課長:
- 代替職員については、移行の申し出を受けた中でその都度対応し、会計年度任用職員や短期の職員で対応していくため、現時点で具体的な人数は想定していない。
(23:08) 岩田委員:
- 制度導入で利用者がすぐに増えるのか、徐々に増えるのか、見通しを質問しました。
(23:38) 職員副課長:
- 部分休業や育児短時間勤務の制度自体は現在もあるため、この移行確認制度が始まった途端に人数が大幅に増えることは想定していない。徐々に制度の認知が進み、利用者が増えていくと考えている。
(24:02) 小谷委員:
- この条例改正によって期待される効果について、市はどのように考えているか質問しました。
(24:28) 職員副課長:
- 労働者の仕事と育児の両立ニーズを職員に伝え、制度をきちんと利用してもらうことで、仕事を辞めずに続けられることを目的としている。育児での離職などを減らしたい。
(25:05) 小谷委員:
- 現状の制度と比べて、どういった点で期待される効果が進んでいくのか質問しました。
(25:27) 職員副課長:
- 現在も制度はあるが、今回の改正で義務付けることにより、制度を知らなかったために利用しなかったという事態を防ぐ。職員にとって制度が認知され、利用されるものと考えている。
(26:37) 原委員:
- 配偶者が妊娠出産の場合、男性職員が申し出る現状と、申し出を増やすための積極的な周知はどの程度行われるのか質問しました。
(27:52) 職員給与係長:
- 男性職員の配偶者妊娠出産の申し出は増えている。事前に申し出がなかった職員については、職員互助会のお祝い金制度の申請時に職員課から案内することも可能。
(28:56) 職員副課長:
- 特定事業主行動計画を定めており、男性育児休業取得に力を入れている中で、男性の育児休業制度を積極的に周知している。
(29:26) 篠原委員:
- 移行確認の具体的な方法と頻度を想定しているか。
- 確認した職員の移行にどの程度まで配慮されるのか質問しました。
(29:56) 職員副課長:
- 移行確認は、妊娠出産の場合は職員課で制度説明と移行確認を行い、所属長にも確認を促す。3歳未満の子を養育する職員については、把握の方法から検討中だが、職員課が把握し、所属長にも説明・移行確認をしてもらう形を検討。最低2回は行う形を考えている。
- 移行への配慮については、全てを叶えることは難しいが、叶えられるところまで叶え、難しい部分については丁寧に説明していく。
(31:42) 篠原委員:
- 配慮の具体例(例を挙げるなど)を求めました。
(32:00) 職員副課長:
- 勤務時間や業務量の調整は所属との相談の中で叶えられる要素が大きい。勤務場所の調整も職員課として考える余地は十分ある。
(32:41) 篠原委員:
- この制度導入によって、新たに予算や人員配置が生じるのか質問しました。
(33:12) 職員副課長:
- 人員の補填の関係で予算的なものは生じる可能性はあるが、その都度必要な人を確保していくため、現時点では具体的な人数は答えられない。
議案第56号 小田原市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
(33:57) 企画部長:
議案説明資料5〜6ページについて説明。
- 目的: 地方公務員の育児休業等に関する法律の改正に伴い、育児を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を一層容易にするための部分休業制度の拡充を行う。
- 主な改正内容:
- 部分休業の承認内容の変更: 従来の1日につき2時間を超えない範囲での請求から、どの時間帯でも30分単位で承認可能に変更。
- 新たな形態の部分休業の設定: 1年につき条例で定める時間を超えない範囲で請求できる部分休業を新たに設定(非常勤職員以外の職員は77時間30分、非常勤職員は勤務日数に10を乗じた時間)。承認は一部の場合を除き1時間単位。
- 部分休業の請求期間等: 毎年4月1日〜翌年3月31日までの期間ごと。
- 部分休業の申し出の内容を変更できる特別の事情: 申し出時に予測できなかった事実が生じたことにより、子(小学校修学の始期に達するまで)の養育に著しい支障が生ずると任命権者が認める事情とする。
- 部分休業の承認の取り消し自由の変更: 上記特別の事情により職員が部分休業の内容を変更した時とする。
- 施行日: 令和7年10月1日。
(36:59) 小谷委員:
- この条例改正によって得られる効果やメリットについて質問しました。
(37:22) 職員副課長:
- 今回の改正の大きな部分は「新たな形態の部分休業の設定」、特に「2号部分休業」の導入。これは保育園の行事や子供の病気対応など、日頃の送迎には必要ないが、突発的な育児対応に柔軟な働き方ができる制度である。
(38:31) 小谷委員:
- 非常勤職員への支援拡大や男性の育児休業取得促進に繋がるか、見解を質問しました。
(38:53) 職員副課長:
- 会計年度任用職員は年次休暇や看護休暇が正規職員より少ないため、この2号部分休業が使用できるようになれば大きなメリットがある。
- 男性職員にとっては、日頃の送迎は妻に任せつつ、行事参加や病気対応など突発的な育児対応に柔軟に対応できるため、夫婦で育児を支える形がより多くできるようになる。
(39:56) 原委員:
- 請求から承認まで速やかに行われるのか、また請求手続きは煩雑ではないのか質問しました。
(40:29) 職員給与係長:
- 承認までの期間は、現在の制度と同様に、申請があれば速やかに審査し対応しているため、時間がかかるものではない。
- 手続きも申請様式提出と必要書類(出生届の写し、母子手帳の写し等)の添付であり、煩雑ではないと考えている。
(41:42) 岩田委員:
- 部分休業が就業時間中の好きな時間で取れるようになることで、管理職の労働時間管理の手間はどの程度変化すると考えているか質問しました。
(42:15) 職員副課長:
- 休みを取る際の申し出は従来と同じ。労働時間管理は、本人がシステム入力し、上司がシステムで確認することで対応する。
(42:55) 岩田委員:
- 中抜けが増えることで、人員配置の手間が増えると思うが、実際どのくらい変動すると見込んでいるか。
- 上長の立場としては考えることが増えるため、制度が利用しづらくなる可能性がある。制度趣旨の徹底と、代替人員の増強はどのように考えているのか質問しました。
(44:17) 職員副課長:
- 上長への制度周知はきちんと行いたい。中抜けで休む職員は増える可能性があるが、実際にどれくらいになるかは運用してみないと分からない。状況を見ながら人員補充は考えなければならないと認識している。
(45:22) 岩田委員:
- 具体的な数字で見込んで対応しているわけではないとのことだが、職場の同僚への理解も必要。制度導入後1年で状況を把握し、対応を考えるといった検証をどのように行うのか質問しました。
(45:58) 職員副課長:
- 制度開始後、所属や本人から「取りやすい」「取りにくい」といった意見や、中抜け対応についての相談が職員課に寄せられると思う。それらの相談を踏まえて対応を考えていきたい。
(47:04) 岩田委員:
- 30分や1時間の中抜けに対し、単に人を配置するだけで対応できるのか。その人員配置が制度利用を妨げないように、どの程度人員を増強する考えがあるのか質問しました。
(47:49) 企画部長:
- この制度ができて、新たに休む職員が大幅に増えるというイメージは実際にはない。職員は元々時間単位で休める制度があり、お子さんの都合で休むことは上司と相談してうまく時間を使って行われていた実例が多い。今回の制度は、時間を使わずに休めるようになるという切り替わりが多いと考える。職員課で今後、この制度によって新たに増える人がいれば、どの程度必要か把握しながら検討していく。
- (50:36) 質疑が終了し、議案第56号の審査が終了しました
議題:議案第50号 令和7年度小田原一般会計補正予算(総務部関係)
- (51:51) 総務部長より、歳入の繰越金(2億4198万円増額)と、ウクライナ避難民支援事業(日本赤十字社への寄付金172万4000円計上)についての説明がありました。
- (53:51) 小谷委員:ウクライナ避難民の現在の人数と、その方々の滞在期間について質問。
- 総務課長:現在3名が小田原市で生活しており、それぞれ令和5年1月、3月、6月に来日。
- (54:33) 小谷委員:3名が小田原でどのように快適に過ごしているか、情報があれば質問。
- 総務課長:うち2名は働いて生活していることを確認。
- (55:01) 篠原委員:ウクライナ避難民支援事業の具体的な支援内容について質問。
- 総務課長:住宅支援(支援住宅への入居)、一時金(1人あたり10万円)、家具・重機等の給付金(1人あたり20万円)を支給。
- (55:54) 篠原委員:日本語教育、医療支援、就労支援の状況について質問。
- 総務課長:就労支援は商工会議所を通じてマッチングを実施。言語学習や医療支援は市としては行っていない。
- (56:59) 岩田委員:日本語等の支援をしていないことについて、対象者からの要望の有無、長期避難者への地域社会への適応支援の要望の有無、今後の支援事業の変更について質問。
- 総務課長:日本語学校の支援要望は出ていない。個別に総務課職員が生活の困りごとを聞きながら支援している。
- (58:09) 岩田委員:今回の長期支援事業における教訓や課題、今後の活用について質問。
- 総務部長:今回の事業は国からの依頼によるもので、特段市として定めるものではないが、今後も国や県と連携し、小田原市としてできることがあれば実施していく。
- (1:00:46) 質疑が終了し、議案第50号(総務部関係)の審査が終了しました。
議題:議案第50号 令和7年度小田原一般会計補正予算(市民部関係)
- (1:01:24) 市民部長より、自治会活動事業(富水地区自治会連合会へのカラー印刷機購入補助220万円)と、報償基金積立金(寄付金3万円の積立て)についての説明がありました。
- (1:04:44) 岩田委員:カラー印刷機の選定は自治会連合会が行い、補助金を支出する理解で良いか。また、印刷機は泉に設置され、一般利用者も利用可能か質問。
- 地域政策課長:選定は自治会で行い、泉に設置されるため一般利用者も利用可能。
- (1:05:54) 岩田委員:印刷機の管理は連合が行う理解で良いか質問。
- 地域政策課長:その理解で良い。
- (1:06:14) 篠原委員:コミュニティ助成事業で毎年印刷機に充てているが、他に活用できる対象事業はないのか質問。
- 地域政策課長:自治会からの要望で印刷機が多いが、過去には証作成や地図配布、広報掲示板等への活用事例もある。今後も協議していく。
- (1:07:53) 篠原委員:自治会組織ではない地域コミュニティ組織(まちづくり委員会など)もこの助成事業を活用する余地があるか質問。
- 地域政策課長:その解釈で良い。
- (1:08:34) 質疑が終了し、議案第50号(市民部関係)の審査が終了しました。
議題:議案第50号 令和7年度小田原一般会計補正予算(防災部関係)
- (1:09:46) 防災部長より、災害時速報体制の強化(避難所運営用パーテーション購入費100万円)と、防災対策積立金(寄付金4601円の積立て)についての説明がありました。
- (1:12:12) 原委員:パーテーション25張は25の避難所に1張ずつ配置されるのか。どのように使う予定か。単価と何人用か質問。
- 防災部副部長:25の広域避難所に1張ずつ配置。プライバシー確保のため世帯ごとの休息スペースとして想定。2人用で、単価は約3万6千円から7千円。
- (1:13:28) 原委員:1つの避難所に2人用のパーテーション1張では意味があるのか。もっと安価なものを複数購入した方が良いのではないか質問。
- 防災部副部長:1避難所1張では足りないが、これで終わりではなく計画的に整備していく。今回は寄付金の範囲内で最適と判断。安価なものも検討したが、品質を考慮した。
- (1:16:03) 原委員:1張もらった運営委員会側へのアドバイスは。入室やコミュニケーションが難しい方への利用など、アドバイスをつけて配布するのか質問。
- 防災部副部長:県からのテントタイプのものや市で備蓄しているものもあり、それらは入室や更衣室等に利用。1張しかないものについては、他のものもあることや今後も購入していくことを説明していく。
- (1:18:11) 岩田委員:パーテーションの対応年数は。テント型ベッドを準備しているなら、テント型を優先すべきではないか。避難所のプライバシー確保資材は何種類あるか質問。
- 防災部副部長:対応年数は不明。テント型は高価なため、限られた予算で多くの休息スペースを確保するためパーテーションを選定。資材はパーテーションタイプが250張(今回追加25張)、テントタイプが県配備165張、市備蓄125張。
- (1:21:09) 岩田委員:今回購入するパーテーションは、市が順次整備しているパーテーションタイプのものと理解して良いか質問。
- 防災部副部長:その理解で良い。
- (1:21:38) 岩田委員:各広域避難所に何張配置されるか。現行計画の想定配備数に対する充足率は。
- 防災部副部長:各避難所への具体的な配置数は不明。計画量は610張に対し、現在250張整備済みで今回25張追加で合計275張。
- (1:22:50) 岩田委員:パーテーション全体の配置は、想定避難者数に対して比率で按分するのではなく、単純に避難所の数で割ったものになるのか質問。
- 防災部長:全員にベッドと家族単位で保護するパーテーションを設置していく考え。急には難しいが順次揃えていく。避難者の数に応じた数を揃えられるようにしていく。
- (1:25:05) 岩田委員:今回寄付された25張を、想定避難者数が少ないところに一挙に配置し、国際水準に到達させるようなモデルケースを作る考えはなかったのか。平均的に配置する理由を質問。
- 防災部副部長:市内全域を見渡して均等に避難所の環境を改善していく考えに立っているため、今回は均等配置とした。
- (1:26:54) 原委員:今回の事業は現行計画に位置づけられているのか、計画的に導入している結果なのか質問。
- 防災部副部長:計画は災害備蓄計画に沿って整備している。今回のものもそれに沿っている。ただし、能登半島地震の教訓を踏まえ、計画自体は見直しを検討している。
- (1:28:02) 原委員:計画の見直しは現状しっかり進んでいるのか質問。
- 防災部副部長:令和7年3月に神奈川県の地震被害想定調査が発表されたことを受け、現在プロジェクトチームを立ち上げて見直しを進めている。
- (1:29:00) 質疑が終了し、議案第50号(防災部関係)の審査が終了しました。
議題:議案第63号 財産の取得について(ラップ式トイレ一式)
- (1:29:46) 防災部長より、自動ラップ式トイレ116台の取得(落札価格5097万6200円)についての説明がありました。設置場所はマンホールトイレの整備が見込めない13小学校と2中学校の計15校。
- (1:31:22) 原委員:今後マンホールトイレが整備された学校にラップ式トイレが配備されるのか。ラップ式トイレに間仕切りはあるのか、設置場所はどこか質問。
- 防災部副部長:マンホールトイレ整備完了後は再配置を検討。間仕切りはセットに含まれており、屋内での使用が可能。
- (1:33:17) 岩田委員:消耗品(バッテリー、フィルム、凝固剤、ウェットティッシュ等)の互換性について質問。
- 防災部副部長:消耗品やバッテリーは本体に付属する純正部品。互換性については現在調査中であり、今後補充する際に視野に入れて調べていく。
- (1:34:52) 岩田委員:災害時に使うものであるため、年代によって型番が違う場合も考慮し、互換性についてきちんと調査し、委員会に報告するよう要望。
- 防災部副部長:再度補充する際には、互換性の点も含めて委員会に報告する。
- (1:36:26) 小谷委員:ラップ式トイレの設置によって、マンホールトイレの整備方針はどのように変わるのか質問。
- 防災部副部長:ラップ式トイレはマンホールトイレ整備のスピードが上げられない間の不足を補完するためのもの。マンホールトイレ自体の整備計画に直接影響はない。
- (1:37:37) 小谷委員:ラップ式トイレの整備によってマンホールトイレ整備の緊急性が低くなっているのではないか。予算の優先順位を見直すべきではないか質問。
- 防災部副部長:それぞれメリット・デメリットがあり、様々なトイレを整備することで柔軟に対応できる。マンホールトイレの優先順位を下げているつもりはない。
- (1:39:15) 質疑が終了し、議案第63号の審査が終了しました。
議題:議案第64号 財産の取得について(高規格救急自動車)
- (1:40:52) 消防長より、高規格救急自動車2台の取得(落札価格5904万8000円)についての説明がありました。
- (1:43:30) 小谷委員:落札価格と予定価格の開きが大きい理由について質問。
- 救急課長:物価高騰と電動ストレッチャーの導入により価格が上がっている。
- (1:44:59) 小谷委員:会社の金額の差額が大きい理由について再度質問。
- 消防総務課長:入札の結果、日産神奈川販売株式会社が頑張った結果である。
- (1:46:04) 小谷委員:最初の答弁と矛盾があるため、再度説明を要望。
- 救急課長:1回目の答弁は予定価格の昨年との違いを説明したもので、今回の入札価格は日産が提示した金額である。
- (1:47:50) 岩田委員:過去5年間の予定価格に対する契約金額の割合と比較してどうか。今後の予定価格設定に見直しがあるか。今回の救急車と既存の救急車の質的な違いは。今後何年くらい技術的な変化がないと見ているか質問。
- 消防総務課長:過去5年間のデータは手元にないため後日提出。
- 救急課長:現在所有する14台に技術的な差はない。電動ストレッチャー自体の進化はあるが、企画自体は同じ。
- (1:50:58) 岩田委員:今回の調達価格は物価変動だけでなく技術的な変化によるものと説明があったため、今後もこの価格水準が続くのか、さらに技術的な変化で価格が上がる見通しはどうか。過去の予定価格と落札価格の落札率の差の動向について、消防の見解を資料で提出するよう要望。
- 救急課長:今回初めて電動ストレッチャーを導入したため、今後も同様の金額になっていくと思われる。
- 消防長:車両自体が年々高騰しており、新たな資機材(電動ストレッチャーなど)の開発があれば、予定価格は上昇傾向にあると考える。
- (1:56:07) 消防長:予定価格と落札価格の変動は、その時々のメーカーの事情によるところが大きく、完全に予言はできない。
- (1:56:45) 原委員:今後電動ストレッチャーがスタンダードになるのか。電動ストレッチャーは乗せる時が電動なのか、患者の乗り心地などメリットは何か質問。
- 救急課長:県内各消防本部で導入が進んでおり、今後も慎重に検討していく。上下運動だけでなく、救急車への引き込み・出し入れも電動。先行導入した職員からは、人力よりスムーズで乗り心地が良いとの話を聞いている。
- (1:58:59) 質疑が終了し、議案第64号の審査が終了しました。
議題:議案第65号 財産の取得について(高度救命処置式等)
- (1:59:22) 消防長より、高度救命処置式等の取得(落札価格4290万円)についての説明がありました。
- (2:01:29) 質疑なし。
- (2:01:34) 質疑が終了し、議案第65号の審査が終了しました。
議題:議案第66号 財産の取得について(消防団活動他)
- (2:01:57) 消防長より、消防団活動服等の取得(落札価格1814万496円)についての説明がありました。
- (2:03:26) 小谷委員:落札価格と予定価格の開きが大きい理由について、予定価格の見積もりが甘かったのではないか質問。
- 消防課長:物価高騰の影響もあるが、本市消防団は規模が大きく、大手メーカーや市内業者が参入意欲を示した結果、安価で落札できた。
- (2:04:59) 小谷委員:予定価格を出す際の積算根拠について再度質問。
- 消防課長:当初は活動服1着あたりの見積額から算出した。購入数が多いため単価が下がったと考えられる。
- (2:06:07) 岩田委員:前回の活動服更新時との差額は物価変動によるものか、他に価格変動要因があるか質問。
- 消防課長:前回更新は平成19年で、当時のデータは持ち合わせていない。
- (2:07:07) 質疑が終了し、議案第66号の審査が終了しました。
採決
- (2:07:23) 議案第50号(所管事項)、議案第55号、議案第56号、議案第63号、議案第64号、議案第65号、議案第66号の7件について一括採決が行われました。
- (2:08:33) 岩田委員:職員の働き方に関わる議案について、制度変更による人員充足等の変動が不明確であった点を指摘しつつ、賛成の討論を行いました。
- (2:09:48) 全員賛成により、全ての議案が原案の通り可決されました。