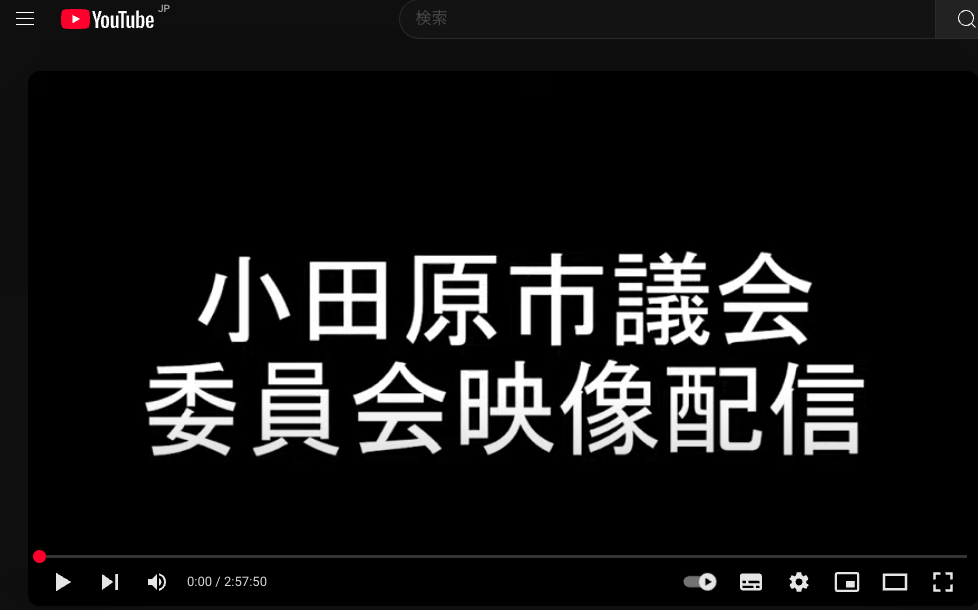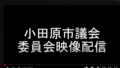- 厚生文教常任委員会 (R7.6.13 PM) 議事録
- 1. 搬送ロボットと患者アプリの導入について
- 2. オンライン診療と神奈川県からの補助金による機器購入について
- 3. 小田原市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について
- 4. 令和7年度小田原市一般会計補正予算所管事項(教育部関係)について
- 5. 小田原市立学校条例の一部を改正する条例について
- 6. 陳情第53号 マイナ保険証の保有の有無に関わらず国民健康保険加入者全員に資格確認書を発行することを求める陳情
- 7. 陳情第54号 マイナ保険証の保有の有無に関わらず国民健康保険加入者全員に資格確認書を発行する手続きを行わせるための対応を求める意見書を国に対して提出することを求める陳情
- 8. 陳情第52号 豊かな学びの実現 教職員定数改善を図るための2026年度政府予算にかかる意見書提出を求める陳情
- 9. 所管事務調査について
厚生文教常任委員会 (R7.6.13 PM) 議事録
1. 搬送ロボットと患者アプリの導入について
- 城戸委員 (03:28): 搬送ロボット導入による人員削減の見込みと汎用性、および患者アプリ導入後のランニングコストについて質問。他自治体付属病院での7つの危機導入実績と効果事例についても尋ねました。
- 経営管理課副課長 (04:50): 搬送ロボットは人件費削減よりも、医療人材不足の中での業務効率化と本来業務への集中を目的としていると説明。薬剤や検体以外の診療材料の運搬も可能であり、他病院では買い物支援やストレッチャーの自動化事例もあると回答。ランニングコストは搬送ロボットが年間110万円程度で、患者アプリは検討中とのことでした。
- 経営管理課長 (07:07): 補助対象機器の他院での導入実績として、血管造影装置ハイブリッド手術室は神奈川県内13病院、ハイブリッドERは3病院、放射線治療装置は10病院での導入実績があると述べました。
- 城戸委員 (08:12): 7つの機器が補助金を見込んで予算計上されたものか再確認しました。
- 経営管理課 (08:44): 債務負担行為を組んでおり、元々導入予定であったと回答。
- 城戸委員 (08:52): 搬送ロボット導入後の確認作業やチェック体制に必要な人員について再質問しました。
- 経営管理副課長 (09:25): ロボットは遠隔でモニタリングされ、医療従事者はタブレットで操作することで自動運搬されると説明。
- 城戸委員 (09:59): 医療の充実のため、ロボットなどの活用を市民のために進めてほしいと要望しました。
2. オンライン診療と神奈川県からの補助金による機器購入について
- 神戸委員 (10:25): オンライン診療の将来的な拡大範囲と方法、および補助金で購入する機器の選定方法(入札かプロポーザルか)について質問しました。
- 経営管理副課長 (11:47): オンライン診療は、来院にコストやリスクが伴う重度障害者や遠距離居住者にメリットが大きいと説明し、今後の検討課題としました。
- 経営管理課長 (12:35): 機器選定は、市立病院内の「機械器具導入機種選定委員会」で機能や金額を比較検討し、その後、町内の入札審査委員会を経て入札を行うと回答しました。
- 神戸委員 (13:16): 発言内容の訂正後、オンライン診療導入による民間病院とのバランスの取り方、および機器購入におけるメーカーとの癒着防止のための監視体制について質問しました。
- 経営管理副課長 (15:28): オンライン診療は導入ハードルが高く、まずはスモールスタートで始め、民間病院の状況も踏まえて拡大を検討するとしました。
- 経営管理課長 (16:21): 選定委員会は医師、看護師、事務方が参加し、公平性を保つため入札参加条件と審査委員会で適切に判断していると説明しました。
3. 小田原市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について
- 鈴木敦子委員 (20:16): 病院名称変更の提案元、議論された期間、決定経緯、およびパブリックコメントの意見数とその内訳について質問しました。
- 経営管理課長 (20:56): 新病院開院に向けた建設準備委員会で議論され、市立病院運営審議会に諮られた経緯を説明しました。
- 経営管理科副課長 (21:55): パブリックコメントは8人から9件の意見があり、賛成・反対・その他がそれぞれ3件ずつだったと報告しました。
- 鈴木敦子委員 (22:36): 運営委員会のメンバー構成、交通標識等の名称変更にかかる概算コスト、そして市民や患者にとっての名称変更のメリット・デメリットを明確にするよう求めました。
- 経営管理科副課長 (23:58): パブリックコメントの内訳を再度確認しました。
- 経営管理課長 (24:26): 審議会メンバーは医師会、自治会、薬剤師会など多岐にわたると説明。メリットは新病院が高度で専門性の高い医療を提供する拠点病院であることを明確にすること、デメリットは「市立病院」という名称が市民に馴染んでいる点にあると述べました。
- 鈴木敦子委員 (26:24): 患者からの意見聴取は行われたか、今後行う考えはなかったのか、また運営委員会で「市立病院」の名称を残すべきという意見はなかったのか質問しました。
- 管理副課長 (27:38): パブリックコメント募集のため、市立病院にも用紙を設置していたと回答。
- 経営管理課長 (27:54): 審議会では名称変更を肯定的に捉える意見の他、「小田原」をひらがなで表示すべき、市民にとって「市立」が重要、機能をアピールするなら現在の案が良いといった意見があったと説明しました。
- 鈴木敦子委員 (28:54): 「総合医療センター」という名称は市民にとって分かりにくい可能性や、かもめ図書館の例を挙げ、市民に定着している「市立病院」の名称を変えることの疑問を呈しました。
- 安藤副市長 (29:59): 外部からの視点では「総合医療センター」の方が機能が充実した病院としてアピールでき、より多くの患者に選ばれる可能性があると説明。一時的に名称の定着に時間がかかるとしても、中長期的には小田原市の病院の機能が認識されると考えていると述べました。
- 城戸委員 (33:39): パブリックコメントの意見数の少なさや意見の割れ具合から、市民の意見を十分に吸い上げていないと感じるとし、名称を早急に決定する理由について質問しました。
- 経営管理副課長 (34:44): 新病院の建設に伴う看板設置のスケジュールがタイトであり、他の準備にも影響が出るため、このタイミングでの決定が必要だったと説明しました。
- 城戸委員 (35:57): 意見数が少ない理由として、広く意見を聞く努力が不足していたのではないかと尋ねました。
- 経営管理科副課長 (36:26): 市民意見の募集は行っていたため、意見を聞いていない状況ではないとの認識を示しました。
- 城戸委員 (36:50): 意見数が少なくても進めている理由が不明だとし、名称変更にかかるコストについて、他自治体の事例で概算費用が分かれば教えてほしいと求めました。
- 経営管理科副課長 (37:30): 建て替えのタイミングでの名称変更はコストを抑えられると理解しており、このタイミングがベストだと述べました。
- 城戸委員 (38:18): 名称変更の理由について再度疑問を呈し、患者数が増えたなどのメリット事例があれば教えてほしいと尋ねました。
- 経営管理科副課長 (39:31): 患者が増えた事例は把握しておらず、名称変更の目的は新病院の機能や地域拠点としての役割を分かりやすく示すためであると強調しました。
- 病院管理局長 (39:50): 病院の名称変更は公共施設として重要であり、新病院建設という何十年かに一度のタイミングを活かし、市民や関係者に病院の多様な機能や地域拠点としての役割をイメージしてもらうためであると説明しました。
- 城戸委員 (41:18): 市民の意見が少ない現状で名称変更を進めることへの懸念と、名称変更に伴うコスト(税金)について考慮し、市民の意見をしっかりと吸い上げる努力を要望しました。
- 神戸委員 (42:30): 市長が名称変更は独立行政法人化を目的としないと答弁したことに対し、市立病院が将来的に独立行政法人化を目指していた経緯との整合性について質問しました。
- 病院管理局長 (43:24): 市立病院は公益企業法の全部適用を受けており、今後の形態は経営強化プランで整理中だが、今回の名称変更は独立行政法人化を目的とするものではないと明確に回答しました。
4. 令和7年度小田原市一般会計補正予算所管事項(教育部関係)について
- 桒畑委員 (54:50): 老朽化対策として、中学校のエレベーター更新事業の優先順位と計画、および昭和57年から使用しているエレベーターの部品供給終了について事前に想定できたか尋ねました。
- 保険給食課長 (55:59): 中学校の給食エレベーターは昭和時代に設置された6基のうち、今回の更新で一通り終わると説明。平成17年設置のものも20年経過しており、今後順次更新を検討すると述べました。
- 鈴木敦子委員 (57:06): 三の丸小学校放課後児童クラブの移設について、保護者へのアンケート実施の有無、今後の説明方法、国道を渡る際の安全確保策、普通教室確保困難の検討経緯、検討期間について質問しました。
- 教育総務課長 (58:30): 保護者へのアンケートは行っていないが、7月上旬に利用者向け説明会を予定していると回答。国道横断時の安全確保については、運営スタッフによる迎え入れや行政職員による誘導を行うとしました。普通教室確保のため、多目的室転用やプレハブ建設なども検討したが、学校運営上困難と判断し移設を決定。検討期間は3ヶ月間だったと説明しました。
- 鈴木敦子委員 (1:01:04): 安全確保は「当面の間」ではなく継続的に必要ではないか、グラウンドがないことへの代替案、移設先の使用期間、中学校でエレベーターがない学校の有無について質問しました。
- 教育総務課長 (1:03:07): 安全確保は運営スタッフによる迎え入れを継続し、行政職員の誘導は「当面」だが安全確保を最優先とすると回答。グラウンド代替として、室内でも運動できる施設を設置予定。移設先は5年程度使用する予定としました。
- 保険給食課長 (1:04:47): 中学校は4校、小学校は1校に給食エレベーターの設置がないと説明しました。
- 鈴木敦子委員 (1:05:44): 三の丸小学校の5年間の根拠と、その後より良い場所が見つかった場合の再移設の考え、中学校のエレベーターがない学校への設置優先順位について質問しました。
- 教育総務課長 (1:06:37): 児童数推計などを総合的に勘案し、今後も慎重に運営場所の方針を打ち出すと回答しました。
- 保険給食課長 (1:07:31): 新たなエレベーター設置については、建物の構造や費用を考慮し、大規模改修時に合わせて検討したいと述べました。
- 鈴木敦子委員 (1:08:08): 子供たちの公平性を考慮し、エレベーターの新規設置も早急に検討してほしいと要望しました。
- 鈴木和宏委員 (1:08:42): 三の丸放課後児童クラブの移動時の安全確保(コースルール徹底、危険箇所把握)と、事業費の内訳について詳しく質問しました。
- 教育総務課地域教育推進長 (1:09:59): 事業費の内訳は、建物駐車場賃借料、備品購入費、消耗品費、光熱水費、電話委託料であると説明しました。
- 教育総務課長 (1:10:47): 歩くコースは現状直線距離を考えているが、今後委託業者と現地確認を行い、危険箇所の把握に努めるとしました。
- 学校施設担当課長 (1:11:27): 普通教室の増設委託料は、間仕切り壁や設備移設、内装改修、黒板やロッカー設置を含むと説明しました。
- 鈴木和宏委員 (1:12:09): 国道へのスロープ付近の危険性から、ドライバーへの注意喚起の工夫を要望しました。また、費用の妥当性はどのように確保されたのか尋ねました。
- 学校施設担当課長 (1:12:56): 改修内容は教育総務内で検討し、工事業者からの見積もりを基に、市の工事単価と比較して予算計上したと説明しました。
- 鈴木和宏委員 (1:13:26): 改修後の教室が他の教室と同様の快適な環境になるか確認しました。
- 学校施設担当課長 (1:13:56): 改修後の教室は他の教室と同じ質になる予定だと回答しました。
- 神戸委員 (1:14:14): 学校から児童クラブまでの移動に関して、指導員の配置基準について質問しました。
- 教育総務課長 (1:14:40): 国の基準は児童40人に対し2人以上だが、小田原市はそれを上回る配置基準としており、三の丸小学校児童クラブは10人の運営スタッフを配置していると説明しました。
- 神戸委員 (1:15:20): 長期休暇中の室内活動、急病人対応、低学年の飛び出しなど、手厚い人員配置が必要ではないか。10人体制で足りるのか再確認しました。
- 教育総務課長 (1:16:54): 事前協議では10人体制で運営可能と見込んでいるが、適宜協議を行い、必要であればスタッフ増員も検討するとしました。
- 神戸委員 (1:18:06): スタッフが人員不足を感じた場合、事業者から市へ情報が伝わる仕組みになっているか確認しました。
- 教育総務課長 (1:18:22): その点については情報共有や協議をきちんと行うと回答しました。
- 城戸委員 (1:18:41): 学校図書購入費について、過去の寄付実績と具体的な活用事例を質問。三の丸小学校放課後児童クラブの移転について、今後児童数が増加した場合の対応と、他校との連携(児童クラブの受け入れなど)について尋ねました。
- 教育総務課総務長 (1:20:33): 寄付された図書は、補正予算可決後に学校で図書を購入し、図書室に配置されていると説明しました。
- 教育総務課地域教育推進長 (1:21:42): 新しい施設では120人ほど利用可能と回答しました。
- 教育総務課総務長 (1:21:55): 児童数の予測は難しいが、今後も慎重に見立て、指定変更制度の見直しなども検討し、教室不足にならないよう手立てを講じるとしました。
- 教育総務課長 (1:23:32): 他校との連携は、児童クラブのスペースや学校ごとのカリキュラムの関係で難しいと述べました。
- 城戸委員 (1:23:55): 図書館の古い辞書や絵本の見直し、新しいものの導入を要望しました。児童クラブの児童数増加懸念に対し、他校との連携の余地があるか再質問しました。
- 教育総務課長 (1:25:58): 他校との連携は難しい点が多いとしつつも、そういった考え方もあるという点は受け止め、検討の必要性があるか考える姿勢を示しました。
- 城戸委員 (1:27:03): 児童数の変動が読めない中で、今回の児童クラブを機に、今後全体で話し合いを進めてほしいと要望しました。
5. 小田原市立学校条例の一部を改正する条例について
- 教育部長 (1:27:57): 令和8年4月の小田原市立早川連携型認定こども園、小田原市立橘の子供園の開設に伴い、小田原市立前羽幼稚園及び下中幼稚園を廃止するため、条例を一部改正すること、および学校給食関係の条例も一部改正すると説明しました。適用は令和8年4月1日です。
6. 陳情第53号 マイナ保険証の保有の有無に関わらず国民健康保険加入者全員に資格確認書を発行することを求める陳情
- 陳述者 (1:50:58): 従来の健康保険証の期限切れにより医療現場で混乱が起こる懸念があるとし、マイナ保険証の保有の有無に関わらず、国民健康保険加入者全員に職権で資格確認書を交付するよう求めました。後期高齢者には国が対応するが、国民健康保険加入者にもデジタル不慣れな方が多く、医療機関でのトラブルも増加している現状を訴えました。東京都渋谷区と世田谷区での全戸交付事例も挙げ、混乱を最小限にするためのバックアップ方法として資格確認書の全員発行を要望しました。
- 城戸委員 (1:56:39): 資格確認書を発行することによるデメリットはあるか尋ねました。
- 陳述者 (1:57:07): 費用の上乗せが発生する可能性はあるが、それ以外のデメリットは少ないと考えていると回答しました。
- 福祉健康部長 (1:58:58): 国の方針に従い、国民健康保険加入者全員への一律交付はコスト等を考慮し現状は行わないと説明しました。市民がスムーズに受診できるよう、広報誌やホームページで制度の周知に努めるとしました。
- 鈴木敦子委員 (2:01:00): 7月末の期限切れに関して、医療機関や市民からの問い合わせや意見が寄せられているか質問しました。
- 保険課長 (2:01:17): 現時点では大きな問い合わせは来ていないと回答しました。
- 鈴木敦子委員 (2:01:34): デジタル難民のような方々への対応について、市は手続きをしてほしいという考えか尋ねました。
- 保険課長 (2:02:11): 登録方法はいくつかあるため、身近な方法でマイナ保険証を登録してほしいと回答しました。
- 城戸委員 (2:02:51): 医療機関の機械トラブルにより資格確認書がない場合に、どのような対応がされるのか尋ねました。
- 保険課長 (2:03:36): かかりつけ医であれば過去情報で確認、または保険者資格申立書を記入することで10割負担ではなく通常負担で受診できる手段が用意されていると説明しました。
- 城戸委員 (2:04:18): 保険者資格申立書にマイナンバーのような独自情報の記載も必要か確認しました。
- 保険課長 (2:04:46): 申立書には保険種別、自己負担割合、事業所名、交付時期、氏名、住所、生年月日、性別などを記入すると説明しました。
- 城戸委員 (2:05:40): 記入内容が分からなかった場合どうなるか尋ねました。
- 保険課長 (2:06:09): 現場の医療機関の判断になるとし、どこまで求められるかは運用次第であるとしました。
- 福祉公部長 (2:06:50): マイナンバーカード保持者には資格情報のお知らせが発送され、リーダー故障時などにそれで確認できると補足しました。
- 城戸委員 (2:07:23): 資格情報のお知らせは常時携帯するよう周知されているか、また申立書の記入内容の判断が現場に重くのしかかるという認識で良いか尋ねました。
- 保険課長 (2:07:59): 広報誌などでマイナンバーカードと一緒の携帯をアナウンスする予定。現場の責任については、利用者の過大な請求やトラブルにならないよう、国も制度設計をしていると思うと述べました。
- 城戸委員 (2:09:09): 国の制度が進む中で、現場の判断に責任が委ねられるのは避けるべきだと指摘。市民の負担が増えることへの懸念も示し、市として国に対し、陳情の趣旨(マイナ保険証の有無に関わらず全員に資格確認書発行)を伝えるべきだと要望しました。
- 採決 (2:10:22): 陳情第53号について採択の賛否を諮った結果、賛成少数で不採択と決定しました。
7. 陳情第54号 マイナ保険証の保有の有無に関わらず国民健康保険加入者全員に資格確認書を発行する手続きを行わせるための対応を求める意見書を国に対して提出することを求める陳情
- 陳述者 (2:13:12): 陳情の趣旨は前件と同様で、保険証廃止と資格確認書が適切に届かない問題点を強調しました。特に、オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関(紙レセプト請求の医療機関)では、患者の資格確認が困難になるケースが想定されると説明。多くの市民が資格情報のお知らせを携帯していないため、医療機関での対応が困難になる恐れがあるとし、全国の医療関係者から問い合わせが殺到している現状を報告。システム導入の難しさや高額な費用、高齢の医師への説明の困難さを訴えました。こうした地域医療を支える医療機関が疲弊すれば、住民が困ると強調。これまでも国や県に意見書提出を要望してきたが実現しておらず、まずは国に意見書を提出してほしいと強く要望しました。
- 福祉健康部長 (2:18:07): (執行部として、本件に対する特段の発言はなし)
- 城戸委員 (2:18:23): 現場の混乱は避けられない印象を受けたとし、市民の不要な負担が増えることへの懸念を示しました。国が早急に進める姿勢は、市民の医療アクセスを軽視しているのではないかと指摘し、陳情に賛成の立場を表明しました。
- 採決 (2:19:07): 陳情第54号について採択の賛否を諮った結果、賛成少数で不採択と決定しました。
8. 陳情第52号 豊かな学びの実現 教職員定数改善を図るための2026年度政府予算にかかる意見書提出を求める陳情
- 陳述者 (2:22:20): 本陳情は、豊かな学びの環境実現のための教育予算増額と教職員定数改善の推進、および多様な専門性を持つスタッフの増員・常勤化の2点を国に意見書として提出するよう求めるものと説明しました。
- 教職員定数改善について: 義務標準法により定められた教員定数は改善されていないにもかかわらず、ICT教育、金融教育など「〇〇教育」が増加し、公務負担が増大していると指摘。いじめや不登校の児童生徒数が過去最多を更新し、生活困窮家庭やヤングケアラーなどの課題も多様化している中で、教員の勤務実態調査では小学校で14.2%、中学校で36.6%の教員が過労死ラインにあることが明らかになっていると述べました。持続的安定的な教職員確保のためには、抜本的な定数改善が必要だと強調。
- 多様な専門性を持つスタッフの増員・常勤化: 不登校生徒数が34万人を超え過去最多である現状に対し、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどの専門職員が学校現場に不可欠であると訴えました。しかし、神奈川県では配置が不足しており、市町村が市費で対応せざるを得ない状況にあると説明。教育の質の向上のため、全ての学校に専門スタッフが常勤として配置されるよう、国による予算措置を求めました。
- 鈴木和宏委員 (2:28:22): 本陳情の財源について、また国に負担を求めるものか確認しました。
- 陳述者 (2:28:59): 委員の認識通り、国の予算として財政措置を求めていると回答しました。
- 鈴木敦子委員 (2:30:25): 現場の教職員だけでなく、子供たちの学びの環境改善に必要であり、スタッフの増員・常勤化は教員、子供双方にとって良いことだと考え、採択を表明しました。
- 鈴木和宏委員 (2:30:57): 学校運営における国と市の予算割合について言及し、国に予算増加を求めることは小田原市の自主性を損なう懸念があるとし、反対の立場を表明しました。国が「生徒が減ったから教員を減らす」と判断する材料になるべきではないと述べました。
- 城戸委員 (2:32:00): 子供の環境改善は重要であり、教職員の負担軽減、少人数学級の実現、多様な教育活動の充実につながると述べました。小田原市にとって教育予算の充実は重要であるとし、陳情に賛成の立場を表明しました。
- 鈴木和宏委員 (2:33:14): 教員の苦労や現状は理解しており、改善は必要だが、その方法が本市の自主性を損なうことに懸念がある点を補足しました。
- 採決 (2:33:57): 陳情第52号について採択の賛否を諮った結果、賛成多数で採択と決定しました。
- 意見書提出の際の署名は賛成者のみとすることに異議なし。
- 意見書の内容は副委員長一任とすることに異議なし。
- 本会議で不採択となった場合、委員会で決定した意見書の提出は取り消すことに異議なし。
9. 所管事務調査について
- 協議事項:所管事務調査の実施について
- 委員長 (3:39:01): 議長からの発言を受け、本委員会でも所管事務調査を実施したいとし、テーマ案について委員の意見を求めました。
- 神戸委員 (3:39:27): 所管事務調査のテーマとして、学校の施設(小田原市内の36校)のあり方の検討を提案しました。各学校の老朽化などの課題を共有し、将来的な学校の統合・再編なども見据えながら、未来の学校のあり方について調査していきたいと述べました。
- 城戸委員 (3:41:00): 教育の提案も魅力的としつつ、国でも多額の予算が使われている医療費について、その内容を深く知るためにも、医療分野での調査を提案しました。
- 採決 (3:55:10): 所管事務調査のテーマは「学校の施設のあり方」とすることに異議なしと決定しました。
- 調査項目と詳細は次回の委員会で決定することを確認しました。
- 協議事項:視察日程について
- 初期 (3:56:27): 視察は10月から11月にかけて実施され、10月14日〜17日の4日間と11月4日〜7日の4日間が候補日であると説明。第1候補と第2候補を決めるよう求めました。
- 採決 (3:57:37): 例年通り2泊3日の現地視察とすることに異議なしと決定しました。
- 視察日程の調整 (4:01:42): 第1案として10月15日〜17日の2泊3日、第2案として11月4日〜6日の2泊3日で調整を進めることに異議なしと決定しました。
- 視察項目について
- 城戸委員 (4:02:18): 視察候補として大阪府・市を希望しました。理由として、健康のあり方、ワクチンの被害者支援、オーガニック給食の成功事例、米騒動への対応など、厚生文教常任委員会として多岐にわたる項目を見学できる点を挙げました。
- 鈴木和宏委員 (4:03:08): 所管事務調査に絡めた視察先を選定することとし、正副委員長一任とすることを提案しました。
- 採決 (4:03:39): 視察項目については正副委員長一任とすることに異議なしと決定しました。